
「和」という漢字の成り立ちから、和の本質的な意味を独自の目線で、考察していきます。
和(わ)とは、調和や平和を意味する言葉。
人々が互いに協力し、共に生きることを示す概念であり、
対立や争いを避け、共存共栄を目指す姿勢を表す。和は、日本文化の根底に流れる価値観であり、
日本人の行動や思考に深く影響を与えている。
和という漢字は、のぎへん(禾)と(口)と書きます。
禾は穀物の総称で、稲などの穀物が稔って重くなり、穂を垂れている姿を描いている文字だと言われています。

口は、そのまま口を表しているというのが一般的な解釈です。
一方で漢字研究の第一人者、白川静博士によると、口は「祝詞を入れる器の形」であると、解釈されています。祝詞も器も、現代の私たちには、なかなか現実的なイメージが湧きませんよね。器という字にも口がたくさんあるので、神様への願い事をたくさん入れたものが、器という解釈なのでしょうか。
祝詞は、神様への祈りの言葉です。
祝詞とは、祭典に奉仕する神職が神さまに奏上する言葉のことです。
その内容は、神饌(しんせん)・幣帛(へいはく)などを供え、御神徳に対する感謝や称辞(たたえごと)を奏し、新たな恩頼(みたまのふゆ)を祈願するというものが一般的な形です。
神への祈りの言葉を入れる器=口
このように祝詞は、人間が考えた神様に捧げる言葉という解釈が一般的ですが、私はその逆だと考えます。
人間が、神の意を「口」を通して言葉として表現したもの、それが祝詞です。
一般の人が単に言葉を発してもインパクトはないので、神道の神職が我々を代表して、そのような表現を儀式という形で見せてくれています。
神は自ら、表現することができません。人間という表現媒体を通してのみ、自らの意を伝えることができます。
つまり、私たちひとりひとりの口から発せられる言葉には、本来、神の意を表現できるほどの重みがあるということです。
また、言葉にする前には、必ず意があります。意識は、生きている人間に平等に与えられていますが、その意識の源こそが、神そのものです。
「口」とは、単に食べ物を噛んだり、言葉を話す物質的なものではなく、神の意を伝える役割を担うことができる、大切なものです。
口=神の意を伝える言葉が、たくさん(無限に)入っている器
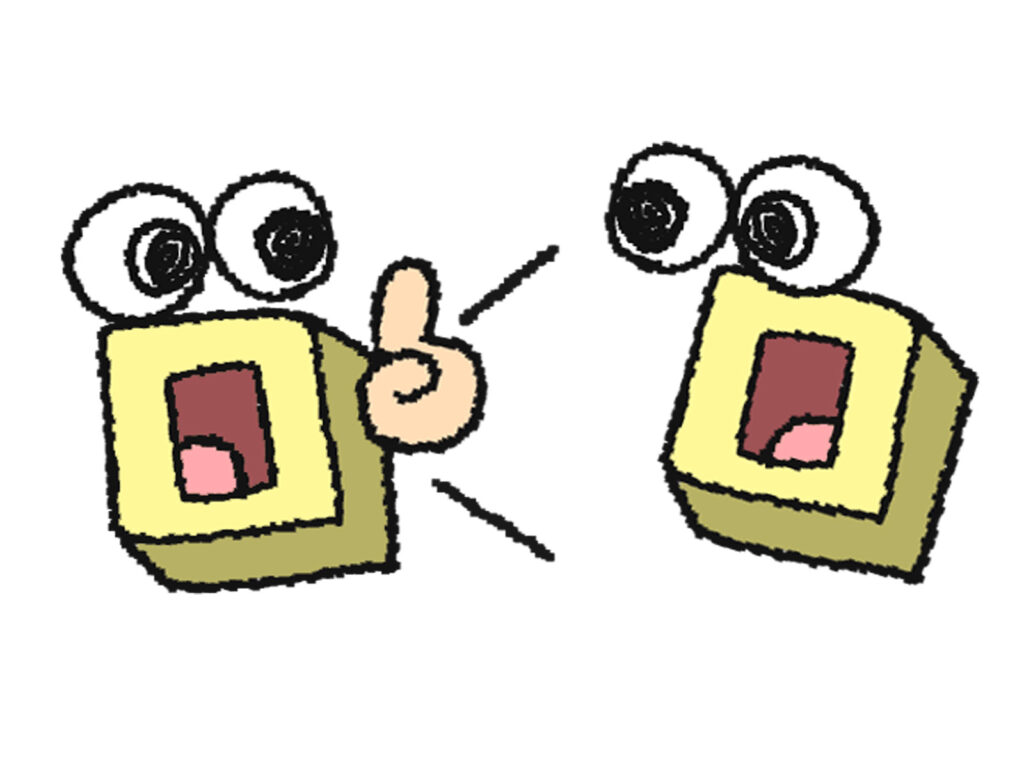
今まで、言葉を話すための口について考えてきました。
口のもう一つの役割は、ご存知のように食べ物を噛み砕き、体内へ送る場所として存在しています。
もうずいぶん前のことになりますが、私が歯科医師をしていた頃、口腔領域の実に不思議な現象を度々目にしていました。その一つが、歯の噛み合わせです。μm単位の調整で、人間の体は劇的に瞬間的に変化します。まさしく、神合わせの領域でした。
私たちは、単なる食べ物という物質を、物質的に歯で噛み砕くことくらいにか「口」について理解していませんが、本当は、見えることだけの話ではありません。
例えば、日本にはお米を神に供える「神米」というものがあります。また、神聖な食べ物という考え方があります。
もっとも原始的な食の思想は神人共食という古代の人々の食べ物に対する信仰である。世界のほとんどの地域には神聖な食べ物とそれを尊ぶ食習慣があった。神や先祖の霊と親しく交わるために食べる神聖な食べ物が定められていたのである。人々の主食となる作物は必ずといってよいほど神聖な食べ物に選ばれ、神が宿る神聖な作物を食べることは即、神を祀ることであると考えられていた。
….古代の人々にとって、食べものは神の力を頂く媒介であるとみなされていた。
食の社会学 13 神人共食の思想 食の社会学研究会代表 橋本 直樹
このように、口=神合わせ というもう一つの重要な意味があります。
以上をまとめると、「和」の漢字の意味が紐解かれていきます。
禾:食べ物の象徴である穀物。それは単なる食べ物としてだけでなく、神が宿る神聖なものとして、表現されています。
口:神の意を伝える言葉を入れる器=口
神聖な食べ物、神が合わさる=口
つまり「和」とは、「神が合わさる」ことを意味しているのです。
日本では足し算+のことを和と言います。合わせるという意味です。何を合わせるのかといえば、神を合わせるという意味です。
たったひとつの宇宙意識 でお伝えしたように、私たちが見ているものには形があり、名前がありますが、見えないものはひとつしかなく、それが神だということです。
食べ物=神、人間=神、山=神、海=神、、、すべて神を表現したものです。神は無限なのですから、あの人、この人、あの国、この国、と見えないものの本質を区切ることはできません。
その中でも口は、言葉として(出)、食べ物が最初に入る場所(入)として、神の出入り口(接点)として、人間の体の中でも五感を通して「神」がわかりやすい、部位になっています。食べ物が、いつの間にか形を変えて私たちの体を作ったり、生命を維持するエネルギーになるのですから、神の御業みわざとしか思えません。

ここで、もう一度最初に戻ってみます。
和(わ)とは、調和や平和を意味する言葉。
人々が互いに協力し、共に生きることを示す概念であり、
対立や争いを避け、共存共栄を目指す姿勢を表す。和は、日本文化の根底に流れる価値観であり、
日本人の行動や思考に深く影響を与えている。
和らぐ(やわらぐ)、和む(なごむ)、調和、平和、和の心、大和など
人間が生活を営む上で「神が合わさる」ことに意識を向けると、素晴らしい日常生活が見えてきます。私たちは、神と共にあります。すべては、神と共に存在しています。
すべてが神ならば、本来は対立や争いをする必要もありません。人間と神は協力して、共に生きています。
・人間と神(陰−と陽+)が合わさって、言葉を紡ぐ。
・食べ物と人間と神が合わさって、人間の体を作り生命を維持する。
・人間と神が合わさって、調和が生まれる。自然との調和は、神と人間との調和。
・人間と神が合わさってこそ、心が和み、平和が訪れる。
「和」そのものが日本を意味しているのですから、私たち和の国の人々には何か大切な役割があるのではないのでしょうか。
さて、次回は神道でいうところの「惟神の道」について、お伝えしたいと思っています。
誤解のないようにあらかじめお伝えしておきますが、私はどこの宗教にも属していません。また過去に、宗教に属したこともありません。神道についても、学問的な知識はまったくありません。時々、私は神という表現をしますが、私たち人間やこの世界、宇宙を創造した存在のことを神と呼んでいます。
誰かをどこかに誘導する意図はないので、私一個人の独り言として聞いてくださるとありがたいです。